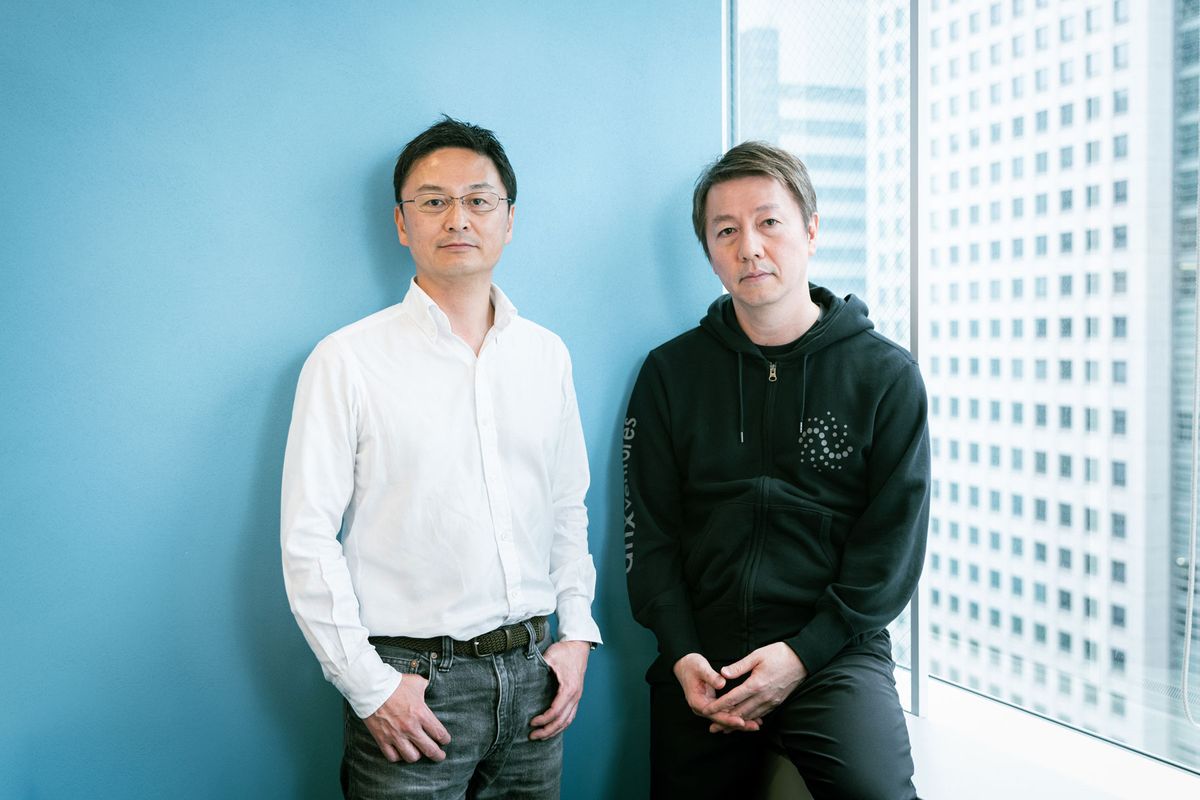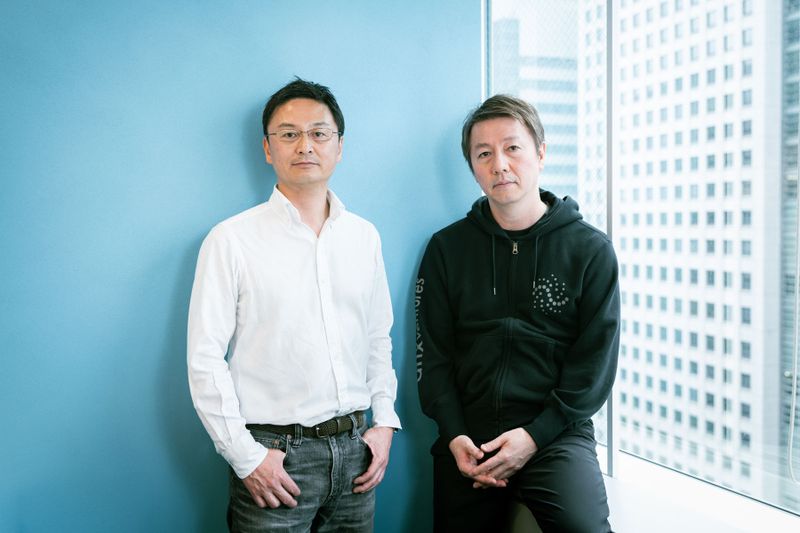日米市場を中心にB2Bスタートアップへの投資を行っているベンチャーキャピタルファンドDNX Venturesが、日本の産業変革に挑む起業家にフォーカス。「社会課題を解く、スタートアップの抱く使命」と題し、連載していく。
第4弾は、経営管理プラットフォームの開発・提供で急成長を遂げ、シリーズB資金調達を発表したDIGGLEの代表取締役 山本清貴をゲストに迎えた。彼らが目指す「予算消化」という言葉がない世界とは。聞き手は「日本の産業が抱える課題解決に高い志をもつ起業家を応援したい」とシードステージから同社とともに歩んできたベンチャーキャピタリスト、DNX Venturesのマネージングパートナー兼日本代表の倉林 陽が務めた。
日本企業が抱えた予算活用の課題
倉林 陽(以下、倉林):予算消化は、年度末に広告予算やシステムの機能開発の発注が突然立て込むという日本企業ならではの悪習だと思うのですが、どうお考えですか。
山本清貴(以下、山本):予算消化という言葉には、各事業部が「いつかのために」と多めに申請した予算を効率的に使えていない実情が現れていると感じます。皆さん、さまざまな予算に対して「もしかしたら使いたくなるかもしれないから、取っておこう」という心理で予算を抱え込みたがるのです。
その結果、期中にマーケティングの予算がないからとやむなく施策を打ち切っておきながら、期末に余った予算をすべて消化するための広告を出稿したり、システムを発注したりしてしまう。つまり、本当に使いたいタイミングで必要なお金を使うことができないわけです。
倉林:たしかに、使いたいときにはお金がないと言われるのに、期末になるとお金の承認が上がってくるという話はよく聞きます。
山本:そこには、日本企業の縦割り文化や、情報の非対称性といった根深い課題があります。つまり、経営側と現場との間に存在する意識のギャップですね。定性的な話になりますが、コロナ禍でDXは加速したものの、会計領域やHR領域、経費精算や請求書受領を含めバックオフィスのマッピングを見たときに、経営管理だけが取り残されてしまっています。DXの空白地帯と言ってもいいかもしれません。
経営管理は非常に重要な業務にも関わらず、依然として属人的に進められています。営業の現場では、案件の状況が変わったら条件や規模を即座にアップデートしますが、そうしたリアルな数字は経営管理のデータには入らず、ざっくりとした数字に置き換えられてしまうでしょう。
たとえば、IT部門が年間で数億円の予算を持っているとしても、月々に管理する金額の内訳には大規模プロジェクトの費用もあれば個人の携帯電話代もあって、粒度も期間もバラバラです。それを特定のタイミングで報告しろと言うと、8900万円のところを1億円と入力してしまうかもしれません。
その結果、期末になるまでどこにいくら余っているかが見えなくなってしまいます。経営管理の本質はヒト・モノ・カネのリアルタイムなアロケーションですが、「予算は多く取って少なく使う」文化が、機会損失をもたらしているのです。

経営管理のクラウド化が進む未来を信じて
倉林:DIGGLEは2016年の創業時からぶれることのない思いで事業に邁進されていますが、経営管理という経営の根幹に関わる領域で起業された背景をお聞かせください。
山本:僕はSaaSが登場する前、エンタープライズソフトウェアの世界にいました。当時のセールスとしては、顧客情報をクラウド上に預けるサービスが普及するなんて、想像もできませんでした。しかし、クラウドベースのCRMソフトウェアであるSalesforceがあっという間に世の中を変えていったのはご存じの通りです。
「個人事業主ならともかく、大手上場企業が会計やHRの情報をクラウド上に預けるわけがない」という思い込みも、freeeやマネーフォワード クラウド、HR Techが登場して、覆されました。僕が起業したのは、まさにそんなタイミングです。まだ今のような市場はなかったものの、「経営管理という非常に重要な業務が、属人的な表計算ツールで行われ続けるわけはない。いずれ必ずクラウド化する」と確信していました。
その未来が10年後に来るのか、20年後に来るのかはわからなかったし、それまで僕らがやりきれるのかという不安がなかったわけではありません。でも、この領域にクラウドの波が来ることに疑いの余地はなく、そこにベットし続けてやろうとは思っていました。
倉林:「マーケットがあるから参戦したらうまくいくだろう」ではなく、市場がないときから信念を持ち、逃げずに課題に向き合い続けてこられたのがすばらしいです。シード期には厳しい評価もあったかと思いますが、2023年のシリーズA以降、競合案件での勝率において優れた成果を上げ、DNXの投資先の中でも群を抜いた成長率を記録されていますね。
山本:ありがとうございます。市場がない中での8年間は苦しいこともありましたが、確信していた「クラウド化する未来」が今このタイミングでやってきたのかなと感じています。
倉林:ガバナンス改革が進んだことや、コロナ禍でのDXの加速といった要因が重なり、日本企業の経営管理に対する意識が変化したのでしょう。急成長市場になったときに、しっかりと磨き込んだプロダクトを持てていたことが大きいと思います。
確信できた経営管理プラットフォームの定量的なベネフィット
倉林:DIGGLEはお客様の課題にどのようにアプローチできるのでしょうか。
山本:創業時から、DIGGLEは経営の意思決定に役立つソリューションであるはずだと考えていました。しかし「経営の意思決定」は魔法の言葉というか、どんな領域でも言えてしまうんですよね。本質的な意思決定とは何を指しているのかを議論して、「リソースのリアロケーションをできるようにすることが経営の大きな仕事ではないか」という結論にたどり着きました。
Excelから抜け出し、データが早く経営に届くだけでは、インパクトが出せません。しかし、「予算は多く取って少なく使う」文化では、余ったお金が積もり積もるとかなりの額になります。その予算の消化状況を細かく可視化すれば、リアルタイムで期中の予算に対して割り当てていくことができる。それこそが経営管理の本質的な役割であり、その役割を担えるのがDIGGLEだと感じたのです。
倉林:DIGGLEを導入したことで成果が出たエピソードがあれば、ぜひお聞かせください。
山本:定量的なベネフィットを確信できたのは2024年の9月のことです。ある上場企業のユーザーから、「DIGGLEのおかげで年間数十億を動かせるようになった」というお言葉をいただきました。期中でも、余っている予算が回ってきたり、必要性を報告すればきちんと予算が割り当てられたりする。経営報告が自分にもリターンのある大切な行動だと事業部側が理解したことにより事業部と経営企画の信頼関係が構築され、リアルタイムな数値の可視化が全社に行きわたった結果、カルチャーが変わってきたと教えてくれました。
倉林:すばらしい変化ですね。意識の高い会社だからこそ、変化を感じやすいのでしょう。
山本:はい。予算を抱え込む文化から必要な時に使える文化へ変容することで、会社のお金がうまく回るようになるのだと思います。
8年言われ続けた「顧客が愛するプロダクトかどうか」
倉林:我々DNXはシードから全ラウンドで出資を行い、8年にわたってDIGGLEに伴走してきました。この間、事業の転換点や困難な局面もあったかと思いますが、DNXの存在がどのような支えとなったか、印象的なエピソードがあればお聞かせください。
山本:DNXの支援の本質だと思うのですが、「顧客が愛するプロダクトかどうか」ということをずっと問い続けてくれていますよね。僕は営業出身なので、創業して数年は「とにかく売れるプロダクトでなくてはならない」という目線でやってきました。そんな僕に、倉林さんは「数を追わなくていい。それよりも2〜3社でいいからファンを作って」と言ってくれましたが、当時はその言葉の意味が全然わからなかったんです。売り上げがないとシリーズAはできないし、お金が尽きたらどうするんだ、と。
倉林:僕の説明が足りなかったのかもしれないですね(笑)。
山本:本当の意味で追い込まれていないと理解しきれないのかもしれません。シリーズAではお客様へのアップセルやグロースレートは非常に大事なので、そこにばかり目が行きがちです。でも、「広告費を使うことで短期的なMRRを底上げできたとしても、プロダクトが本質的に使われているかどうかはチャーンレートを見ればわかる」と教えてもらいました。それがシリーズA、ひいてはシリーズBに到達する契機だったと思います。
倉林:最初の頃は幅広く攻めていて、チャーンレートも高かったですよね。でも、やっぱり焦点を絞って注力し、質の高いMRRを積み上げることが重要でしたから。
山本:「シリーズAへのマイルストーンの一つとしてARR1億円を実現しても、一年経ったらARRが下がっているなんてことは普通に起こる」と言われたことが印象に残っています。シリーズAのために一旦ARR1億円を頑張っただけなのか、そこを通過点として突き抜けていく会社なのか。後者になるには質の高いMRRを積み上げていくしかありません。それを達成することで我々を信頼し、お金だけでなく人の投資もしてくださったことが、御社から得られた一番大きなものだと思っています。

予算消化という言葉がない世界を目指して
倉林:シリーズBの資金調達を経て、DIGGLEが描く次なるステージやビジョンをお聞かせください。
山本:ヒト・モノ・カネのリアロケーションは、大きな社会的インパクトを生み出します。日本企業は、年度末に集中して広告を出したりシステムを発注したりして、予算を消化していますが、DIGGLEはここを変革していきたいのです。期中の、本当にお金を使いたいときに使っていれば、3月に余ることもなくなります。それを定量的に実現して、予算消化という言葉がない世界をつくる。DIGGLEはそこに向かって挑戦をしていきたいです。
倉林:期中に予算の適正分配ができれば、投資も加速しますね。
山本:はい、日本企業の現場管理者は、予算消化を含めて「合わせられている」という意識を持っていることが多いです。しかし、予実を合わせることと、本当に欲しいタイミングで使いたいことに使うことには、大きな隔たりがあります。データドリブンな経営の意思決定をし、投資を加速させるには、その意識のギャップをなくすことが必要です。
日本でも、CFO直下のミニCFOとして事業のKPI分解やモデリングを支援するFP&Aというポジションが少しずつ普及してきていますが、スキルのある人材を市場で見つけるのは簡単ではありません。しかし、DIGGLEをAIと連携させることで、会計のリテラシーに関係なく示唆を得られたり、複雑なモデリングが必要なものでも簡単にレポートを出せたりと、FP&Aの業務を代替する機能を提供していけるのではないかと思っています。
倉林:DIGGLEが予算消化のない世界をつくり、FP&Aを代替していけたら、日本経済への貢献という役割も果たせそうですね。シリーズBの資金調達というすばらしい第一コーナーを回り、ここからどんな軌跡を描いていくのか、楽しみにしています。
DNX Ventures
https://www.dnx.vc/jpfund/top
やまもと・きよたか◎DIGGLE 代表取締役。早稲田大学ファイナンス研究科修了後、PeopleSoft、Oracle、Inforなど米系ERPベンダーで11年にわたり会計・CRM・SCM領域の営業/アライアンスを担当。その後、デジタルマーケティングスタートアップでセールスを率いた際の「予実管理に苦しむ」経験からDIGGLEを創業。
くらばやし・あきら◎DNX Ventures マネージングパートナー兼日本代表。富士通、三井物産にて日米のITテクノロジー分野でのベンチャー投資、事業開発を担当。MBA留学後Globespan Capital Partners、Salesforce Venturesで日本代表を歴任。2015年DNX Venturesに参画。これまでにSansan、マネーフォワード、アンドパッド、カケハシ等、日本を代表するSaaS企業に多数の投資実績を持つ。